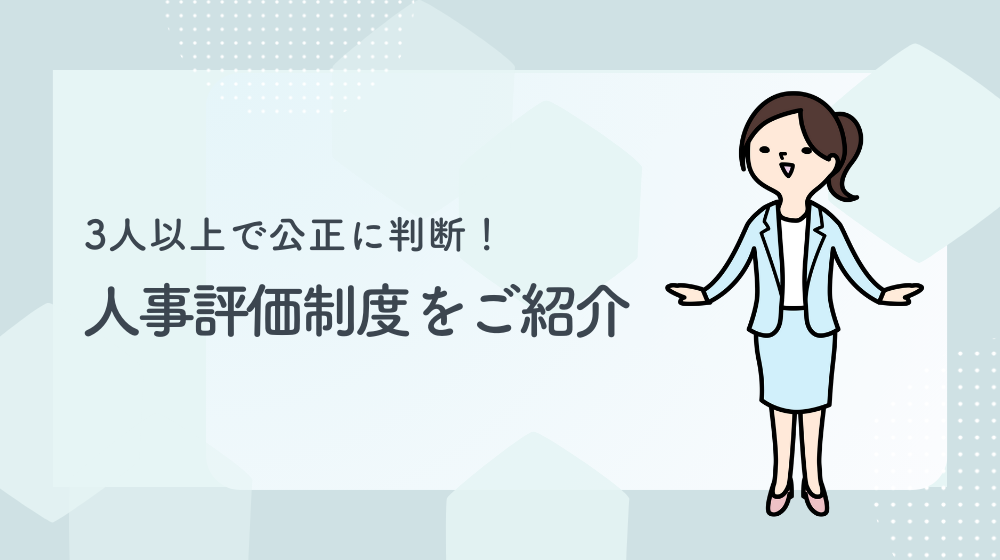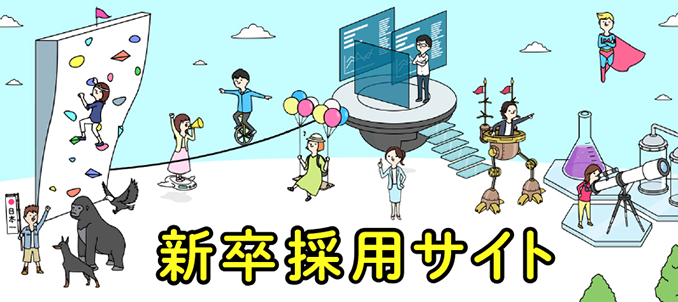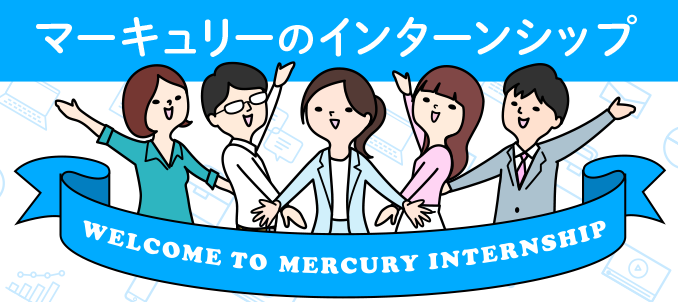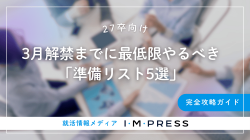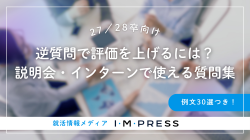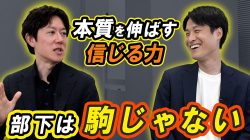\3人以上で公正に判断!/人事評価制度の中身を公開!マーキュリーが「納得できる評価」を目指す理由
こんにちは!株式会社マーキュリーの広報担当です!
お正月に地震があり、当たり前の大切さ・かけがえのない
家族の絆の大切さを改めて実感しました。
被災地の方は今でも落ち着かない毎日を
過ごされていると思います。
1日も早い復興を願っております。
就職活動や転職活動をするうえで、
「人事評価制度ってどんな仕組みなの?」と気になる方は
多いのではないでしょうか?
- 上司の主観だけで評価されない?
- 評価に透明性ってあるの?
- 頑張った分はちゃんと認めてくれる?
今回は、あまり情報が出ていないマーキュリーが目指す
「納得感のある評価制度」について、
仕組みや背景を詳しくご紹介していきます!
自身で言うのもおこがましいのですが、
タレントマネジメントシステムを導入し、
人事評価制度の整備、頑張っています!
※この記事は5分で読めます。
*この記事を書いたのはこんな人*
《名前》Y.W
《略歴》
中途入社でマーキュリー歴はもうすぐ10年!?
マーキュリーでは新規事業の立ち上げや採用業務を経験し、現在は採用広報を担当。
やんちゃな2人の男の子のママ。
目次
マーキュリーの人事評価制度とは?
マーキュリーでは、全正社員に対して
「年2回(半期ごと)」の評価制度を導入しています。
ベースとなるのは「能力評価シート」。
この評価シートには、職種や部署ごとに最適化された
評価項目が設定されており、業務の違いによって評価に
著しい偏りが出ないよう工夫されています。
たとえば営業職とバックオフィスでは
求められるスキルや成果が異なるため、
それぞれに合った尺度でパフォーマンスを可視化します。
さらに、評価項目には本人が設定する定量目標(数字)と
定性目標(行動・意識)の両方が含まれているため、
単に数字を追うだけでは測れない頑張りや工夫も
評価の対象となります。
評価の流れは?ステップごとに分かりやすく解説!
マーキュリーの評価は次のようなステップで行われます。

STEP1|目標設定
半期ごとのスタート時に、上司と一緒に定量・定性の目標を
設定します。ここでは本人の意思も尊重され、
「やらされる目標」ではなく「自分で決めた目標」として
仕事に向き合う土台をつくります。
STEP2|中間面談
期の途中で上司と進捗を確認します。
目標に対する取組状況や軌道修正が必要かを共有し、
課題がある場合はフォローの機会にもなります。
STEP3|自己評価・一次評価
期末には、本人による自己評価と直属の上司による
一次評価が実施されます。
このとき、評価内容は定性的な記述と定量結果の
両方で構成されます。
STEP4|二次評価・最終判定
ここがポイントです。
マーキュリーでは、最低でも3名以上が評価に関与します。
一次評価者の上司(課長や部長)が二次評価を実施し、
最終的な調整は人事または役員クラスによって行われます。
この「多面評価」体制によって、
個人の主観が入るリスクを最小限に抑え、
公正な判断を実現しています。
STEP5|フィードバック面談
評価結果は面談でフィードバックされます。
「なぜこの評価なのか」
「どこが良かったか」
「どこを伸ばせば次の評価につながるか」
を丁寧に伝えることで、社員の納得度を高めています。
どうして3人以上で評価するの?
「一人の上司の判断に偏りがあるのでは?」
「相性が悪いと不利にならない?」
こうした不安をなくすために、
マーキュリーでは多面的な評価プロセスを導入しました。
複数名で評価するメリットはたくさんあります。

- 感情や相性に左右されにくい
- 本人の強み・成長を多角的に見られる
- 特定の上司の価値観に縛られない
- 評価結果の納得感が高まる
もちろん、評価者には事前に研修や評価基準のすり合わせも
行われており、「人によって甘辛が違う」といった
ばらつきが出にくいよう配慮されています。
評価の結果はどう反映される?
評価は結果で終わるものではありません。
マーキュリーでは、評価結果をさまざまな形で
活用しています。

- 昇給や賞与の査定
- 昇格や役職登用の判断
- 異動や配属の参考材料
- 人材育成プランの構築
たとえば、ある社員が「チームでの調整力」に
優れていると評価された場合、
将来的にマネージャー候補として研修を受ける
ことがあります。
また、「挑戦意欲」や「学習姿勢」が評価された若手には、
新規事業の立ち上げメンバーとして声がかかることも。
つまり、評価制度は社員のキャリアを後押しする
“未来へのヒント”でもあるのです。
社員の声を反映して、制度もアップデート
評価制度は「一度つくったら終わり」ではありません。
マーキュリーでは、年に一度、制度そのものの見直しを実施。
人事部や現場の管理職だけでなく、
一般社員からのフィードバックもヒアリングし、
実際に以下のような改定が行われています。
- 評価項目をより実態に近づける
- 面談時間の確保
- 評価基準に“プロセス”を重視する項目を追加
「業務内容に合っていない評価項目があった」
「面談の質が人によって差がある」といった声を反映し、
常にブラッシュアップされています。
働きがいを支える“納得感ある評価”を目指して
評価制度は、社員のモチベーションや働きがいを左右する
重要な仕組みです。
マーキュリーが大切にしているのは、
“成長の機会”としての評価。
- 振り返りの時間を通して、自分の強みや課題に気づける
- 自分の努力がきちんと見てもらえる
- キャリアの方向性が見えてくる
こうした経験の積み重ねが、社員一人ひとりの成長と、
会社全体の活力につながっていくのです。